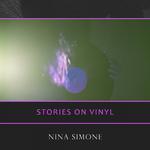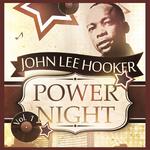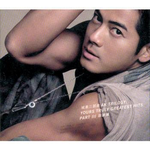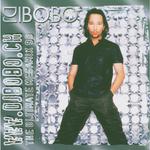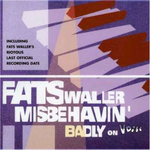姓名: 服部良一 英文名:- 性别:男 国籍:- 出生地:- 语言:- 生日:- 星座:- 身高:- 体重:-
小档案
服部良一(はっとり りょういち、1907年10月1日 - 1993年1月30日)は、日本の作曲家、編曲家、作詞家(「村雨まさを」名義で作品を出している。)。大阪府大阪市平野区出身。ジャズで音楽感性を磨いた、和製ポップス史における重要な音楽家の一人。
小简介
服部良一是日本的流行歌曲的盛行最有功的人,国民荣誉奖获奖者。
代表日本的作曲家的同时,也代表日本的流行歌曲的存在。他的作品,时髦漂亮,而且能证实音乐性的理论。
服部先生的爵士乐,最初在这个时代被培育。大正14(1925)年6月,NHK大阪电视台开业,那里的广播管弦乐团成立了。服部良一先生被选为成员,从指挥者学习古典音乐。
此后,边做广播管弦乐团的工作,边在大阪演奏爵士乐,之后进京,作为作家,编曲家,对唱片公司开始做活动。经过日东唱片进入哥伦比亚,在那里与藤浦洸合发表《离别的布鲁士舞》,在日本的布鲁士舞受好评。
1940年,电影《支那之夜》的主题歌“苏州夜曲”
1944年,指挥上海交响乐团发表《夜来香幻想曲》等。
服部良一先生的诞生100年纪念的年龄,发售纪念专辑,服部克久先生(儿子),隆之先生(孙子)参加演出,代表流行歌曲界的豪华艺人集合,同时也收录克久,隆之牵挂良一新写的新曲,波及到三代的丰富多彩的历史的大集合。
道頓堀のうなぎ料亭「出雲屋」(現いづもや)が、太左衛門橋南ぎわ、カフェー赤玉のまん前にある「角屋」というレストランの支店に少年音楽隊を結成した。1923年9月1日、音楽隊の入隊式が行われたその中に服部良一少年がいた。彼の音楽人生がここに始まったのである。奇しくも関東大震災の起こったその日であった。
1907年(明治40年)10月1日、服部良一は大阪の本庄で土人形師の父久吉と母スエの間に生まれた。小学生のころから音楽の才能を発揮したが、学校を卒業後は商人になるためと、昼は働き夜は商業学校に通うという日々を送る。しかしそんな日々に嫌気のさした彼は姉の勧めで、好きな音楽をやりながら給金がもらえる出雲屋少年音楽隊に一番の成績で入隊する。しかしその2年後に、第一次大戦後の不景気もあって音楽隊は解散してしまう。なお、当初はオーボエを担当したが、粗悪な楽器で満足に音が出ず、サックスとフルートに転向してから著しく進歩を見せたと、後に述懐している。ダブルリードの微妙な調整が必要なオーボエを指導できる人間が当時の関西には存在しなかったのである。
1926年にラジオ放送用に結成された大阪フィルハーモニックオーケストラに入団。ここで指揮者を務めていた亡命ウクライナ人の音楽家エマヌエルメッテルに服部は見いだされ、彼から4年にわたって音楽理論作曲指揮の指導を受ける。ちなみにこのころ、朝比奈隆も彼から指導を受けている。オーケストラの傍らジャズ喫茶でピアノを弾いていた。昭和に入ると服部は、レコード会社の仕事をするようになった。1929年(昭和4年)頃、コッカレコードでサクソフォーンと編曲を担当した。そして、タイヘイレコードの専属となった。1931年(昭和6年)頃には大阪コロムビアで街頭演歌師出身の作曲家鳥取春陽のジャズ演歌の編曲の仕事をした。1933年(昭和8年)2月、服部はディックミネの助言もあり、上京して菊地博がリーダーを務める人形町のダンスホール「ユニオン」のバンドリーダーにサクソフォン奏者として加わった。翌1934年(昭和9年)2月、東京進出をはかったニットーレコードの音楽監督に就任した。
1936年(昭和11年)にコロムビアの専属作曲家となった。入社第一回作品が淡谷のり子が歌う『おしゃれ娘』だった。やがて、妖艶なソプラノで昭和モダンの哀愁を歌う淡谷のり子が服部の意向を汲みアルトの音域で歌唱した『別れのブルース』で一流の作曲家の仲間入りをはたす。その後ジャズのフィーリングをいかした和製ブルース、タンゴなど一連の和製ポピュラー物を提供。淡谷のり子は『雨のブルース』もヒットさせ「ブルースの女王」と呼ばれた。
その後、霧島昇渡辺はま子が共演し、中国の抒情を見事に表現した『蘇州夜曲』、モダンの余韻を残す『一杯のコーヒーから』、高峰三枝子が歌った感傷的なブルース調の『湖畔の宿』など、服部メロディーの黄金時代を迎えた。だが、太平洋戦争が始まると服部の音楽個性であるジャズ音楽は敵性音楽として排除された。よく「服部良一は軍歌(戦時歌謡)を1曲も作らなかった」と紹介されるが誤りである。これは服部本人が軍歌作曲に対し消極的であったことや、その類が不得手であったことなど様々な理由から、これといったヒット曲は無く、量も他の作曲家と比べると少ないことから、そう言われるようになった。1944年(昭和19年)、上海に渡り(これは軍歌作曲の依頼から逃げるためだったという説がある)ジャズの活動の場を求めた。李香蘭と上海交響楽団とともに、『夜来香』をシンフォニックジャズにした『夜来香幻想曲』を発表した。上海交響楽団ではクラシックの指揮も行い、ロッシーニ作曲「ウィリアムテル」序曲で、エディションの違いによるメロディーの相違についてイタリア人イングリッシュホルン奏者(元トスカニーニの下で演奏した)と論争になった事を、後に自伝「僕の音楽人生」で語っている。
第二次世界大戦後は、戦前に実験済みだったブギのリズムを取り入れ(『荒城の月ブギ』を編曲)、笠置シヅ子の『東京ブギウギ』などをヒットさせた。彼女は「ブギの女王」と呼ばれた。服部と笠置のコンビはすでに戦前(1938年)、紙恭輔に招かれ服部が副指揮者、のち総指揮者をつとめた松竹楽劇団時代から始まっていた。笠置の肉体的な躍動溢れる歌唱は、敗戦に打ちひしがれた日本の国民の虚脱感を吹き飛ばす爆発音だった。戦後には息を吹き返した作品もあった。たとえば、二葉あき子が歌った『夜のプラットホーム』(1939年に淡谷のり子が吹込んだが、「出征兵士の士気を殺ぐ」という理由で発禁処分)、霧島昇が歌った『夢去りぬ』がヒットしたのである。ビクターでは灰田勝彦が歌った『東京の屋根の下』など甘く洒落た曲もある。また服部は東宝映画の主題歌でのヒットも多い。戦後の息吹を伝えた『青い山脈』を作曲。東京芸大出身のクラシックの正統派藤山一郎が格調高く溌剌と歌唱し、日本の国民的な流行歌になった。
古賀政男がマンドリンギターを基調にした洋楽調の流行歌から邦楽的技巧表現を重視した演歌のスタンスへと変化したのに対し、服部良一は最後まで音楽スタンスを変えることなくジャズのフィーリングやリズムをいかし、和製ブルースの創作など日本のポップスの創始者としての地位を確立した。日本のポップス界隆盛の最大の功労者である。曲自体も歴史的価値は別にしても今日でも全く魅力を失っていないものが多く、その意味では海外のクラシックやスタンダードポップスの巨人と並べて語るべき存在ともいえる。日本レコード大賞の創設にも尽力した。
1993年1月30日、呼吸不全のため死去。享年85だった。死後、作曲家としては古賀政男に次いで2人目の国民栄誉賞が授与された。なお『青い山脈』を歌った藤山一郎も国民栄誉賞を受賞している。
2007年12月30日、第49回日本レコード大賞にて特別賞を受賞。